JR大宮駅東口徒歩1分のアイシークリニック大宮院の専門医による監修の解説ページです。
埼玉(大宮)のおすすめ炎症性粉瘤の治療について徹底解説
炎症性粉瘤とは、初期段階の粉瘤に細菌が侵入して、炎症や化膿が起きたものを言います。
炎症性粉瘤は、通常の粉瘤から症状が悪化して痛みが伴うようになるので、放置せずにすぐに治療が必要です。
今回の記事では、東京(上野)周辺での炎症性粉瘤の特徴や原因、治療方法について紹介します。
自分が炎症性粉瘤かもしれないと心配な方でも、どのように治療していけば良いのかを丁寧に解説していますので、ぜひとも参考にしてください。
炎症性粉瘤(アテローム)とは?症状や原因とは?
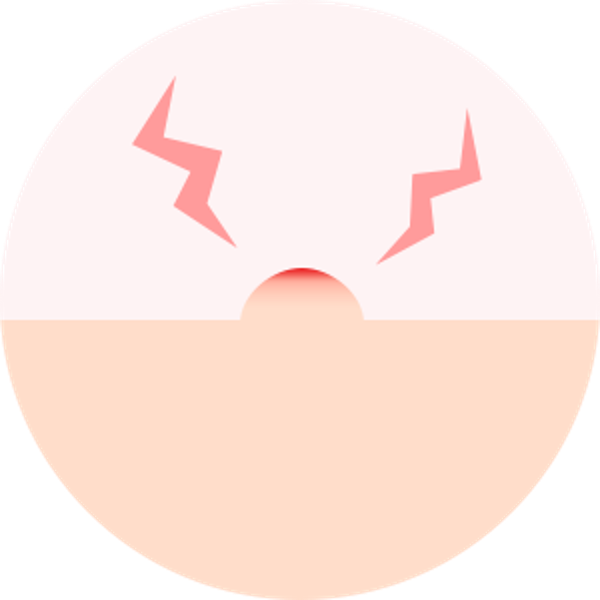
初期段階の粉瘤は、通常痛みはなく、触るとしこりのようなものが感じられる程度です。
しかし、細菌が侵入して炎症を起こすと赤く腫れ上がり、痛みを伴います。
これを炎症性粉瘤(えんしょうせいふんりゅう)または化膿性粉瘤(かのうせいふんりゅう)と呼びます。
※以下、「炎症性粉瘤」という呼称で統一します。
アテローム(粉瘤)を放置するリスク:化膿と悪臭の発生
アテローム(粉瘤)を放置する最大の危険性は、時間の経過とともに内部に溜まった老廃物が腐敗したり、外部から細菌が侵入して感染を起こし、炎症や化膿を引き起こすことです。
- 炎症・化膿の進行:
粉瘤の袋の中は、垢や皮脂が溜まりやすく、細菌にとって増殖しやすい環境です。
特に、皮膚表面と繋がる「へそ」の部分から細菌が侵入すると、あっという間に感染が広がり、炎症を引き起こします。
炎症が起こると、粉瘤は赤く腫れ上がり、ズキズキとした強い痛みを伴うようになります。
さらに悪化すると、内部に膿が溜まり、いわゆる「おでき」のような状態になり、触ると熱を持ち、皮膚の表面が盛り上がってきます。 - 悪臭の発生:
袋の中に溜まった古い角質や皮脂は、細菌の作用によって分解され、独特の不快な悪臭を放つようになります。
この臭いは、自分だけでなく周囲の人にも気づかれるほど強くなることがあり、日常生活や社会生活において精神的な苦痛を与える原因となります。 - 破裂と治療の複雑化:
化膿が進んで内部の圧力が限界に達すると、粉瘤は自然に破裂し、膿や腐敗した内容物が排出されることがあります。
一時的に痛みが和らぐこともありますが、破裂した傷口からさらに細菌が侵入しやすくなり、周囲の皮膚に炎症が広がったり、蜂窩織炎(ほうかしきえん)と呼ばれる広範囲な皮膚の感染症を引き起こしたりするリスクがあります。
また、破裂した粉瘤は、周囲の組織と癒着を起こしやすくなるため、後の手術がより複雑になり、傷跡も残りやすくなる傾向があります。 - 巨大化:
炎症や破裂を繰り返すことで、粉瘤の袋がさらに大きくなり、周囲の組織を圧迫したり、見た目にも大きなこぶとして目立つようになったりすることがあります。
大きくなると、それだけ手術の範囲も広がり、費用や回復期間にも影響します。
このように、アテローム(粉瘤)の放置は、単なる見た目の問題だけでなく、痛みや臭い、さらにはより深刻な感染症のリスクを高め、治療を複雑化させる可能性があります。
そのため、粉瘤の症状に気づいたら、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
アテローム(粉瘤)の自己処理(自分で潰す)は絶対にNG
アテローム(粉瘤)が気になり、見た目や不快感から「自分で潰してしまおう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、粉瘤の自己処理は絶対に避けてください。
自分で潰す行為は、様々な危険なリスクを伴い、症状を悪化させる可能性が非常に高いからです。
自分で粉瘤を潰そうとすると、以下のような問題が発生します。
- 細菌感染のリスク増大:
手の指や爪、不潔な針などを使って粉瘤を潰そうとすると、皮膚に傷がつき、そこから大量の細菌が粉瘤の袋の内部に侵入する可能性が極めて高まります。
これにより、炎症がさらに悪化し、化膿を促進したり、周囲の皮膚に蜂窩織炎などの重篤な感染症を引き起こしたりするリスクが高まります。 - 炎症の悪化と痛みの増強:
無理に潰すことで、内部の袋が破れて内容物が周囲の組織に広がり、強い炎症反応を起こすことがあります。
これにより、激しい痛みや腫れ、熱感といった症状がさらに悪化し、日常生活にも大きな支障をきたすことになります。 - 瘢痕(きずあと)の形成:
炎症や感染がひどくなると、治癒の過程で目立つ瘢痕(きずあと)が残りやすくなります。
特に顔などの目立つ部位では、美容的な問題となる可能性があります。 - 再発のリスク:
粉瘤の根本的な治療は、内容物だけでなく、その原因となっている「袋」ごと完全に摘出することです。
自分で潰しても、袋の一部でも残っていれば、時間とともに再び内容物が溜まり、高確率で再発します。
再発を繰り返すことで、より治療が難しくなることもあります。 - 診断の遅れ:
自己処理を試みることで、医療機関を受診するタイミングが遅れてしまう可能性があります。
稀ではありますが、粉瘤と似た見た目の悪性腫瘍が存在しないわけではありません。
専門医の診察を受けることで、正確な診断と適切な治療方針を立てることができます。
アテローム(粉瘤)は、皮膚科医や形成外科医による適切な処置が必要です。
気になる症状があれば、自己判断で対処しようとせず、速やかに医療機関を受診してください。
専門医が、炎症の有無や粉瘤の大きさ、状態に応じて最適な治療法を提案してくれます。
アテローム(粉瘤)が大きくなる原因と対処法
アテローム(粉瘤)は、一度できると自然に消えることはほとんどなく、多くの場合、時間の経過とともに徐々に大きくなっていきます。
この大きくなる主な原因は、袋の内部で絶えず生成される古い角質や皮脂が蓄積し続けるためです。
- 内容物の継続的な生成:
粉瘤の袋は、皮膚の一部が裏返って形成されたものです。
そのため、袋の内側の細胞は、通常の皮膚と同じように角質を生成し続けます。
この角質や皮脂が袋の内部に溜まり続けることで、粉瘤は徐々に膨らんでいきます。 - 炎症の繰り返し:
粉瘤が炎症を起こすと、周囲の組織が腫れ、粉瘤自体も一時的に大きく感じられます。
炎症が引いても、再び内容物が溜まり、次の炎症が起こるたびにさらに大きくなる悪循環に陥ることがあります。
炎症が繰り返されると、袋の壁が厚くなったり、周囲の組織と癒着したりして、より大きくなる傾向があります。 - 刺激や摩擦:
衣服のこすれや物理的な刺激、圧迫などが原因で、粉瘤が慢性的に刺激を受けると、炎症を起こしやすくなり、その結果として大きくなることがあります。
アテローム(粉瘤)が大きくなった場合の対処法:
粉瘤が大きくなると、痛みや悪臭などの症状が顕著になるだけでなく、見た目の問題や、日常生活での不便さ(服に引っかかる、座る際に邪魔になるなど)が増します。
また、大きくなればなるほど、手術の際に切開する範囲も広くなり、傷跡が残りやすくなる傾向があります。
したがって、アテローム(粉瘤)が大きくなってきたと感じたら、以下の点を考慮し、速やかに医療機関を受診することが重要です。
- 早期の専門医受診:
粉瘤は、小さいうちに治療する方が、手術の負担も少なく、傷跡も目立ちにくく済みます。
大きくなる前に、皮膚科や形成外科などの専門医を受診し、適切な診断と治療方針の相談を行いましょう。 - 適切な手術の検討:
粉瘤の根本治療は、内容物だけでなく「袋」ごと完全に摘出する手術です。
炎症を起こしていない時期に手術を行うのが理想的です。
炎症を起こしている場合は、まず炎症を鎮める処置(切開して膿を出すなど)を行い、その後改めて袋を摘出する手術を検討することになります。 - 自己判断・自己処理の禁止:
大きくなった粉瘤は、内部の圧力がさらに高まっているため、自分で潰そうとすると、感染症や炎症がより重篤化するリスクが高まります。
決して自己判断で触ったり、潰そうとしたりしないでください。
粉瘤の大きさや状態は人それぞれ異なります。
専門医の診断を受け、ご自身に最適な治療法を選択することが、安全かつ効果的な解決への第一歩となります。
炎症性粉瘤の症状とは?
粉瘤は、炎症が起きたり化膿したりすると、赤く腫れ上がり痛みを伴います。
ひどく化膿した場合、皮膚の下の袋状の構造物が破壊され、膿が溜まった状態です。
この状態を膿瘍(のうよう)とも呼び、強い痛みを伴います。
粉瘤が炎症を引き起こす医学的原因
粉瘤の中央に空いているへそ(開口部)の部分から細菌が侵入することが、炎症を引き起こす医学的な原因になります。
そもそも粉瘤とは、垢や皮脂などの老廃物が皮膚の下に溜まることによりできる良性腫瘍のことです。
粉瘤は自然治癒しないため、悪化すると徐々に大きな袋状へと変化していきます。そこに細菌が入りこんでしまうことで炎症が引き起こされるのです。
(※参考:粉瘤とは)
粉瘤の袋の中は、本来、免疫(体の中に入った菌などを排除する機能)を担当する細胞が入っていない構造ですので、細菌感染に弱いという性質があります。
特に、気にして触ったり、潰したりするとそこから細菌に感染し、炎症性粉瘤を引き起こすことがあるので、なるべく触らないようにしましょう。
粉瘤が炎症を引き起こす心理的な原因
「ただのできものだから放置していてもいいだろう」「良性の腫瘍なのだから、放っておいても問題ないはず」という”心理的な油断”から炎症性粉瘤を引き起こしているということも考えられます。
上述したように、粉瘤は自然治癒しないうえ、細菌感染に弱いです。
しかしながら、粉瘤を放置してしまい、炎症を伴い痛みが出てはじめて医療機関へと駆け込む患者様もおられます。
本記事をご覧の皆様は、絶対に放置せず、お早めに粉瘤治療が可能な医療機関へお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
【注意】炎症性粉瘤は破裂する前にクリニックへ

炎症性粉瘤はただの粉瘤から症状が進んで、危険性が増しています。
むやみに触ると破裂する可能性もあるので、その前に病院へ行って受診しましょう。
実は、炎症性粉瘤は日常生活の中にも破裂する危険性が潜んでいるのです。
ここからは、炎症性粉瘤が破裂してしまう原因や、中身が出てきてしまった際の対処法について見ていきましょう。
この内容を知っておけば、受診する前に炎症性粉瘤が破裂することによる症状の悪化を防ぐことができます。
炎症性粉瘤が破裂する原因
炎症性粉瘤は、少しの衝撃でも破裂してしまうことが多いです。
粉瘤が細菌に感染して炎症性粉瘤になると、粉瘤の袋状の構造物が脆くなり、破れやすくなります。
はじめはしこりのような粉瘤も、炎症が進むにつれ次第に皮膚が柔らかくなり、触ると熱を持っているのがわかるようになります。
柔らかくなった状態だと、少し当たったり押さえたりしただけで破裂してしまい、膿が出てくることがあるのです。
袋が破れた場合、周辺に膿が広がりさらに炎症が悪化します。
赤く腫れ上がり、進行すると開口部もただれて広がり、臭いのする膿や袋の内容物が出てきます。
このような自然に膿が排出される状態を「自壊(じかい)」と呼びます。
粉瘤が潰れて中身が出てしまった場合の対処法
日常生活の中で粉瘤が潰れて中身が出てしまった場合は、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。
化膿がひどい場合は、皮膚を切開して内部にたまった膿を出す排膿手術(切開排膿)が行われることがあります。
つまり、外科的手術を伴うことになるので、粉瘤手術に力を入れている病院やクリニックを受診すると良いでしょう。
粉瘤を潰してしまった人もアイシークリニックにご相談ください
「自分で粉瘤を触っていたら破裂してしまい、赤く腫れてしまった」という場合は、すぐにアイシークリニックへご相談ください。
炎症性粉瘤は跡が残りやすいため、できるだけ早く治療するべきです。
痛みが少なく、傷跡も目立ちにくい形での治療を提案していますので、安心してお任せください。
また、当院の粉瘤手術は健康保険適用なので、費用面でも安心して治療ができます。
手術時間は長くても20分程度で完了することが多いので、日帰りでの手術が可能です。
粉瘤のことで少しでもお悩みの方は、そのままにせずにアイシークリニックにご相談くださいませ。
アテローム(粉瘤)の治療法|手術で完全摘出が基本
アテローム(粉瘤)は、薬で治る病気ではありません。
根本的な治療には、溜まった内容物だけでなく、その原因となっている「袋」(嚢腫壁)ごと完全に摘出する手術が基本となります。
このセクションでは、アテローム(粉瘤)の主要な手術方法とその特徴、そして日帰り手術の可能性について詳しく解説します。
アテローム(粉瘤)の手術方法:くり抜き法(へそ抜き法)と切開法
アテローム(粉瘤)の手術方法には、主に「くり抜き法(へそ抜き法)」と「切開法」の2種類があります。
どちらの方法を選択するかは、粉瘤の大きさ、部位、炎症の有無などによって医師が判断します。
| 手術方法 | 特徴(メリット) | デメリット/注意点 | 適用ケース |
| くり抜き法(へそ抜き法) | ・傷跡が小さい: 直径数ミリの小さな穴から内容物と袋を摘出するため、最終的な傷跡が目立ちにくい。 ・回復が早い: 縫合を必要としないか、ごく少数で済むため、術後の腫れや痛みが少なく、治癒期間が短い傾向にある。 ・身体への負担が少ない: 短時間で終了し、局所麻酔のみで行える。 | ・炎症/時期不向き: 炎症が強い場合や化膿している場合は、袋が脆くなって完全に摘出できない可能性があるため、この方法は選ばれないことが多い。 ・再発リスク: ごく稀に袋の一部が残ってしまい、再発する可能性がある。 ・技術を要する: 小さな穴から正確に袋を摘出するため、医師の熟練度が必要となる。 | ・炎症がない状態の粉瘤: 赤みや痛みがない、落ち着いた状態の粉瘤。 ・比較的サイズの小さい粉瘤: 直径2cm程度のものが適応となることが多いが、技術があればもう少し大きくても可能。 ・顔や首など、傷跡を目立たせたくない部位の粉瘤に特に推奨される。 |
| 切開法 | ・確実な摘出: 皮膚を大きく切開するため、粉瘤の袋全体を目視で確認しながら確実に摘出できる。 ・炎症時にも対応可能: 炎症や化膿が強い場合でも、切開して膿を排出し、同時に袋を摘出できる場合がある(ただし、炎症が強い場合はまず排膿処置のみを行い、後日改めて摘出術を行うことも)。 ・再発リスクが低い: 袋を完全に摘出できるため、再発のリスクが極めて低い。 | ・傷跡が残る: 粉瘤の大きさに応じた切開が必要なため、くり抜き法と比較して傷跡が大きくなりやすい。 ・回復期間が長い: 縫合が必要な場合が多く、抜糸までの期間や傷の治癒に時間がかかることがある。 ・身体への負担がやや大きい: 局所麻酔下で行われるが、くり抜き法よりは侵襲性が高い。 | ・炎症を起こしている粉瘤: 赤く腫れていたり、膿が溜まっている粉瘤。 ・サイズの大きな粉瘤: 直径3cm以上の比較的大きな粉瘤や、深い場所に位置する粉瘤。 ・くり抜き法での摘出が困難な場合や、粉瘤が破裂して周囲と癒着している場合。 |
アテローム(粉瘤)のくり抜き法(へそ抜き法)とは
「くり抜き法」は、別名「へそ抜き法」とも呼ばれ、アテローム(粉瘤)の中心にある小さな穴(へそ)や、新たに小さな切開を加えて、そこから専用の器具を使って粉瘤の袋をくり抜くように摘出する手術方法です。
術式の流れ:
1. 局所麻酔: まず、粉瘤とその周囲に局所麻酔を注射します。
2. 小切開または穿孔: 粉瘤の中心にあるへそ、または新たに直径2〜5mm程度の小さな穴を開けます。
3. 内容物の排出: 小さな穴から圧力をかけて、粉瘤内部に溜まった角質や皮脂などの内容物を排出させます。
4. 嚢腫壁の摘出: 内容物が排出された後、袋状の構造(嚢腫壁)を特殊な鉗子などで丁寧に剥がすように引き出し、完全に取り除きます。
この際、袋が破れないように慎重に作業を進めます。
5. 処置完了: 袋が完全に摘出されたことを確認し、通常は縫合せず、そのまま自然治癒を促します。
場合によっては、ごく少量の縫合を行うこともあります。
傷口は小さく、数日でふさがります。
メリット:
・美容的: 最終的な傷跡が非常に小さく、目立ちにくいのが最大のメリットです。
特に顔や首など、美容的な配慮が必要な部位に適しています。
・身体への負担が少ない: 手術時間が短く(通常10〜20分程度)、出血も少ないため、患者さんの身体への負担が軽いです。
・回復が早い: 傷口が小さいため、術後の腫れや痛みが少なく、日常生活への復帰が早いです。
注意点:
くり抜き法は、炎症を起こしていない、比較的サイズの小さい粉瘤に適しています。
炎症が強い場合や、すでに化膿している場合は、袋が脆くなっているため、完全に摘出することが難しく、切開法が選択されることが多いです。
アテローム(粉瘤)の切開法とは
「切開法」は、アテローム(粉瘤)の真上の皮膚を直接切開し、粉瘤の袋全体を目視で確認しながら摘出する、最も確実な手術方法です。
術式の流れ:
1. 局所麻酔: 粉瘤とその周囲に局所麻酔を注射します。
2. 皮膚の切開: 粉瘤の大きさに合わせて、粉瘤の長軸に沿って皮膚を紡錘形(木の葉型)に切開します。
3. 嚢腫壁の剥離・摘出: 切開した皮膚の下から、粉瘤の袋(嚢腫壁)を周囲の組織から慎重に剥がし、完全に摘出します。
この際、袋を破らないように注意深く作業を進めます。
4. 止血・縫合: 出血を止血し、摘出後の皮膚を丁寧に縫合します。
通常は皮膚の表面を糸で縫い合わせます。
5. 処置完了: 傷口を保護するために、ガーゼやテープで覆います。
後日、抜糸のために再診が必要です。
メリット:
・確実性: 袋全体を目視で確認しながら摘出できるため、袋の取り残しが少なく、再発のリスクが極めて低いのが最大のメリットです。
・幅広い適用: 炎症を起こしている粉瘤、化膿している粉瘤、サイズの大きな粉瘤、複雑な形状の粉瘤など、様々な状態の粉瘤に対応可能です。
炎症が強い場合は、まず切開して膿を出す処置を行い、炎症が落ち着いてから改めて袋を摘出する二段階の手術を行うこともあります。
注意点:
切開法は、くり抜き法に比べて切開の範囲が広くなるため、どうしても傷跡が目立ちやすくなります。
特に顔などの目立つ部位では、傷跡の形状や長さが美容的な問題となる可能性も考慮が必要です。
また、術後の回復期間もくり抜き法よりやや長くなる傾向があります。
どちらの方法を選択するかは、患者さんの粉瘤の状態と、傷跡に対する希望などを総合的に考慮し、医師と十分に相談した上で決定することが重要です。
アテローム(粉瘤)の日帰り手術は可能?
多くのアテローム(粉瘤)は、日帰り手術での対応が可能です。
これは、手術自体が局所麻酔下で行われ、比較的短時間で完了するためです。
- 一般的なケース:
小さく、炎症を起こしていない安定した状態の粉瘤であれば、外来で局所麻酔を使って手術を行い、その日のうちに帰宅できます。
手術時間は、粉瘤の大きさや数、選択する術式によって異なりますが、一般的には10分から30分程度で終了することが多いです。
術後は、簡単な処置と術後の注意点の説明を受け、そのまま帰宅できます。 - 日帰り手術のメリット:
- 時間的な負担が少ない: 入院の必要がないため、日常生活や仕事への影響を最小限に抑えられます。
- 精神的な負担が少ない: 慣れない入院生活を送る必要がなく、自宅でリラックスして過ごせるため、精神的な負担も軽減されます。
- 経済的負担が少ない: 入院費がかからないため、総医療費を抑えることができます。
- 例外的なケース(入院が必要となる可能性):
ただし、すべてのアテローム(粉瘤)が日帰り手術で対応できるわけではありません。
以下のような場合は、入院が必要となる、あるいはより慎重な計画が必要となることがあります。- 非常に大きな粉瘤: 直径が数センチメートルを超えるような巨大な粉瘤の場合、出血量が多くなる可能性や、術後のケアが複雑になる可能性があるため、入院して経過観察を行う場合があります。
- 炎症や化膿がひどい粉瘤: 膿瘍(のうよう)を形成して重度の炎症を起こしている場合、まずは切開して膿を排出する処置を行い、炎症が落ち着いてから改めて袋を摘出する手術を数日後に行うケースがあります。
この場合、術後の状態によっては短期入院が必要となることもあります。 - 全身状態が不安定な患者さん: 重度の基礎疾患(心臓病や糖尿病など)をお持ちの患者さんの場合、手術のリスクを考慮して、より管理された環境での入院手術が推奨されることがあります。
- 特殊な部位にできた粉瘤: 関節の近くや重要な血管・神経が近い部位など、手術の難易度が高い場合は、より慎重な対応が必要となります。
基本的には日帰り手術が可能ですが、最終的な判断は、患者さんの粉瘤の状態や既往歴などを踏まえ、医師が行います。
診察時に、日帰り手術が可能かどうか、入院の必要性があるかなどを詳しく確認しておきましょう。
アテローム(粉瘤)の手術費用はどれくらい?保険適用について
アテローム(粉瘤)の手術を検討する際に、多くの方が気になるのが「費用」についてでしょう。
粉瘤の手術は、原則として保険が適用されるため、自己負担額は比較的抑えられます。
ここでは、手術費用の目安と保険適用に関する詳細を解説します。
アテローム(粉瘤)の手術費用の目安
アテローム(粉瘤)の手術費用は、粉瘤の大きさ、存在する部位、炎症の有無、そして選択される術式によって異なります。
また、初診料、検査費用、麻酔代、薬代などが別途かかる場合もあります。
以下に、保険適用(3割負担の場合)の一般的な手術費用の目安を示します。
| 粉瘤の大きさ・状態 | 手術費用目安(3割負担) | 備考 |
| 小サイズ(直径3cm未満、炎症なし) | 約5,000円〜10,000円 | ・主にくり抜き法や小切開法が適用されることが多い。 ・最も費用が抑えられるケース。 ・初診料、診察料、局所麻酔代、処方薬(抗生剤、痛み止めなど)代、術後の消毒・処置費用などが別途かかることがある。 |
| 中サイズ(直径3cm以上5cm未満、炎症なし) | 約10,000円〜15,000円 | ・切開法が選択されることが多い。 ・手術の範囲が広くなるため、小サイズより費用が高くなる。 ・場合によっては病理検査費用が加算されることがある。 |
| 大サイズ(直径5cm以上、炎症なし) | 約15,000円〜25,000円 | ・切開法が必須となるケースが多い。 ・手術の難易度が上がり、時間がかかるため、費用は高めになる。 ・病理検査費用がほぼ確実にかかる。 |
| 炎症・化膿を伴う粉瘤 | 炎症鎮静処置:約3,000円〜5,000円 根治手術(後日):上記プラス各サイズの手術費用 | ・化膿している場合は、まず切開して膿を排出する処置(切開排膿)が行われる。 ・この処置自体にも費用がかかり、その後改めて粉瘤の袋を摘出する根治手術が必要となるため、総費用は高くなる傾向がある。 ・炎症がひどい場合、術後の通院回数が増えることもあり、その分の診察料や処置料がかさむ。 |
【注意点】
・上記の費用はあくまで目安であり、医療機関や地域、具体的な治療内容によって変動します。
・多くの場合、手術費用とは別に、初診料、再診料、検査費用(病理検査など)、麻酔代、処方される薬代(抗生剤、痛み止め、消毒液など)、術後の処置費用などが別途発生します。
これらの費用を含めると、総額は上記の目安より高くなることがあります。
・健康保険組合や市町村によっては、高額療養費制度や医療費助成制度が利用できる場合もありますので、確認してみましょう。
・正確な費用については、受診を希望する医療機関で直接問い合わせるか、診察時に医師や受付で確認することをお勧めします。
粉瘤の手術は保険適用になる?
結論から言うと、アテローム(粉瘤)の手術は、ほとんどの場合健康保険が適用されます。
粉瘤は、医学的に「皮膚にできた良性腫瘍」として扱われ、炎症や感染のリスクがあるため、治療が必要な疾患と見なされるからです。
これにより、患者さんは医療費の自己負担割合(通常3割、1割、2割など)に応じた費用で手術を受けることができます。
保険適用となるケース:
・医学的に治療が必要と判断された場合:
- 粉瘤が大きくなり、生活に支障をきたしている(衣類に擦れる、座る際に痛むなど)。
- 炎症を起こしている、または化膿している。
- 痛みや悪臭がある。
- 見た目が気になる場合でも、医師が医学的必要性を認めた場合。
保険適用外となる可能性のあるケース:
・純粋な美容目的と判断された場合:
- ごく小さく、症状が全くなく、医学的な治療の必要性が低いにもかかわらず、「ただ見た目を綺麗にしたい」という明確な美容目的のみで手術を希望する場合、保険適用外となることがあります。
この場合、「自由診療」となり、費用は全額自己負担となります。
ただし、多くのアテローム(粉瘤)は、将来的な炎症リスクや見た目の変化を考慮すると、医学的な治療対象となりやすいため、純粋な美容目的と判断されるケースは稀です。
診断書と病理検査:
保険診療で手術を行う場合、摘出した組織は通常、病理検査に提出されます。
これは、粉瘤が悪性のものではないか、あるいは他の皮膚疾患ではないかを確認するために行われる重要な検査です。
この検査結果をもって、正式に「アテローム(粉瘤)」の診断が確定します。
医療機関での確認の重要性:
手術を受ける前に、必ず医療機関の受付や担当医に「保険適用になりますか?」と確認しましょう。
特に美容外科クリニックなどでは、自由診療を専門としている場合もありますので、事前に確認することが重要です。
アテローム(粉瘤)は、放置すると炎症や感染などの問題を引き起こす可能性があるため、気になる症状があれば保険診療で適切な治療を受けることをお勧めします。
炎症性粉瘤の治療方法とは

粉瘤が炎症を起こしてしまった場合には、どのように治療するのでしょうか。
炎症性粉瘤の根治治療は外科手術です。
具体的には、「紡錘形切除」と「くりぬき法」の2種類の手術方法があります。
それでは、治療法について1つずつ見ていきましょう。
(1)治療方法「紡錘形切除」
まずは炎症を抑える治療を優先するため、手術の前に「排膿手術」をします。
「排膿手術」とは、先に皮膚を小さく切開して膿を出す(切開排膿)手術を行うことです。
炎症が治ったタイミングで、粉瘤の摘出手術をおこないます。
手術方法は非常にシンプルで、皮膚を紡錘(ぼうすい)形に切開し、粉瘤を取り除いてから縫い合わせるというものです。
綺麗に縫合すれば時間が経つにつれて傷跡も目立たなくなります。
炎症性粉瘤の場合は、無理にくり抜き法を選択するよりも術後経過がよい傾向にあります。
(2)治療方法「くりぬき法(へそ抜き法)
「くりぬき法」とは、特殊なパンチのような道具で粉瘤に小さな穴をあけ、そこから粉瘤の内容物を絞り出した後に、しぼんだ粉瘤の袋を抜き取る方法です。
くりぬき法の特徴としては、「傷跡が小さく、目立たなくてすむ」、「手術時間が非常に短い」などと一般的に言われています。
炎症性粉瘤でも医師の診断に応じて、くり抜き法による粉瘤の日帰り手術も可能です。
→粉瘤(アテローム)の手術について詳しく知りたい方は『粉瘤(アテローム)とは?安心して治療を受ける方法を解説』の記事をご覧ください。
炎症性粉瘤に薬は効くのか?
炎症性粉瘤の治療の場合、炎症を抑えるために抗生物質が投与されることがあります。
抗生物質を飲んで痛みがなくなることもありますが、それは痛みのあった粉瘤の感染がおさまっただけで、腫瘍が取れたわけではないので注意が必要です。
この治療法は感染には効果的ですが、粉瘤の治療としては、それだけでは不十分となります。
粉瘤の根治治療を行うためには、やはり外科手術が必要になります。
炎症性粉瘤の治療料金について
粉瘤の治療にあたっては、診断、検査、手術、病理検査に対して保険が効きますのでご安心下さい。
以下は、アイシークリニックでの治療費の目安になります。
| 粉瘤手術費用(3割負担の場合)のおおよその目安 | ||
| 露出部の場合 | 2cm未満 | 5,000~6,000円程度 |
| 2cm~4cm未満 | 11,000~12,000円程度 | |
| 4cm以上 | 15,000~16,000円程度 | |
| 非露出部の場合 | 3cm未満 | 4,000〜5,000円程度 |
| 3〜6cm未満 | 10,000〜11,000円程度 | |
| 6cm以上 | 12,000〜14,000円程度 | |
| ※病理検査は粉瘤から悪性腫瘍が発生したという報告もありますので、医師の判断に基づき原則として行っております。 ※多発性の場合、近接部位は同時手術も可能な場合がありますが医師の診察によります。 ※上記の手術費用と、診察料・処方料で1,000円程度、検査費用で1,000円程度、病理検査費用で3,000円程度かかります。 | ||
| 粉瘤手術費用(1割負担の場合)のおおよその目安 | ||
| 露出部の場合 | 2cm未満 | 2,000円程度 |
| 2cm~4cm未満 | 4,000円程度 | |
| 4cm以上 | 5,000円程度 | |
| 非露出部の場合 | 3cm未満 | 1,500円程度 |
| 3〜6cm未満 | 3,500円程度 | |
| 6cm以上 | 4,500円程度 | |
| ※令和4年10月1日から、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります ※病理検査は粉瘤から悪性腫瘍が発生したという報告もありますので、医師の判断に基づき原則として行っております。 ※多発性の場合、近接部位は同時手術も可能な場合がありますが医師の診察によります。 ※上記の手術費用と、診察料・処方料で300円程度、検査費用で300円程度、病理検査費用で1,000円程度かかります。 | ||
炎症性粉瘤についてよくある質問
最後に、粉瘤についてよくある質問をご紹介します。気になる部分はご覧ください。
Q粉瘤が赤いですが、痛くはないです。この場合でも病院にいくべきでしょうか?
粉瘤が赤くなっているのであれば、痛くない場合でもクリニックの受診をおすすめします。
軽度の炎症まで進んでおり、そのまま放置すると赤みが強くなり腫れて痛みも伴ってくる可能性があるからです。
手術で摘出することになった場合でも、早めに対応できれば跡が目立たないように治療することができます。
したがって、痛みが無くても粉瘤に赤みがある場合はクリニックを受診しましょう。
Q粉瘤が悪性化することはあるでしょうか?
粉瘤が悪性化することは、極めて稀です。
通常の粉瘤と悪性化したもので、症状や見た目で見分ける方法はないですが、手術で摘出した粉瘤の内容物を病理検査を行うことで、悪性かどうかを判断できます。
埼玉(大宮)で炎症性粉瘤の治療ならアイシークリニック大宮院へご相談ください
本記事では、炎症性粉瘤の特徴や原因、治療方法、料金などについて紹介してきました。
炎症性粉瘤は、通常の粉瘤から症状が悪化しているため、できるだけ早く手術で、根治治療を目指しましょう。
治療後に傷跡が残る可能性を少しでも減らすためにも、放置せず、ご相談に来ていただくことをおすすめしています。
当院では、症状に合わせて痛みが少なく跡が残りにくい手術方法のご提案が可能です。
炎症性粉瘤でお困りの方は、気軽にご相談ください。
アイシークリニックの4つの特徴
(1)結果を重視した専門治療を行います
実績・経験が豊富な専門医たちが患者様の負担を最小限にするため、結果にこだわった治療を行います。

(2)患者様の症状や希望に合わせた治療プランを提案します
患者様の抱える不安や悩みに寄り添いながら、最適な治療プランを提供させて頂きます。

(3)痛みを最小限に!傷跡はキレイに!
幅広い治療方法の中から、患者様の痛みが少なくなるように、施術後もできるだけ影響を残さないような治療を選択します。
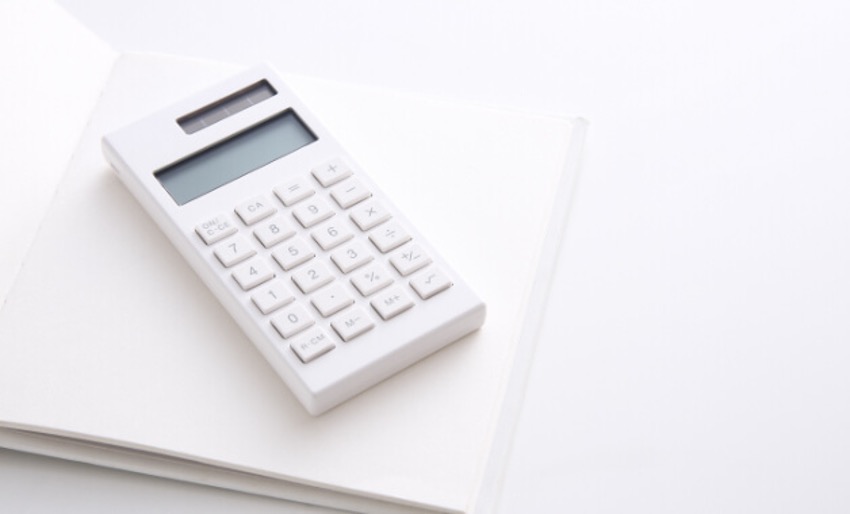
(4)老若男女どなたでも相談しやすいクリニックです
年齢・性別に関係なく、どなたでも相談しやすいようなクリニックの環境作りをしています。
監修者医師
高桑 康太 医師
略歴
- 2009年 東京大学医学部医学科卒業
- 2009年 東京逓信病院勤務
- 2012年 東京警察病院勤務
- 2012年 東京大学医学部附属病院勤務
- 2019年 当院治療責任者就任
佐藤 昌樹 医師
保有資格
日本整形外科学会整形外科専門医
略歴
- 2010年 筑波大学医学専門学群医学類卒業
- 2012年 東京大学医学部付属病院勤務
- 2012年 東京逓信病院勤務
- 2013年 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院勤務
- 2015年 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院勤務を経て当院勤務



